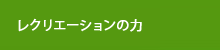保育・幼児教育の現場で、レクはもっと活用できる!
 柿本 因子 氏
柿本 因子 氏
(比治山大学短期大学部幼児教育科教授)
長年保育の現場に携わりながら、 大学での人材育成もしてきた柿本因子さん。 柿本さんは、保育者にとって大切なのは、子どもの心に灯をともす体験を手渡すことだと考え、大学で保育を学ぶ学生たちにも、その大切さを伝える授業を行っています。
五感を養う体験が、保育の現場に求められている
「今、子どもたちの五感が危ぶまれているんです。"五感"って、人間の基礎ですよね? 人間は五感を使わないと、生活できない。昔は、川でバシャバシャ泳いだり、木登りをしたり、路地裏でたくさんの子どもたちがコマや缶蹴りをしたりと、五感を磨く環境がたくさんありました。でも、今はそんな環境が少なくなったばかりか、公園も子ども一人では危なくて行けなくなってしまった。つまり、昔は普通に生活していれば身についた感覚が、鈍くなってきてしまった。これからは、そういった五感を養う場を、保育の現場が担っていかなければならないんです」
こう話すのは、柿本因子さん。実際、柿本さんが園長を務める幼稚園では、五感を磨く遊びがたくさん行われているそうです。
「例えば、グラウンドの泥を使っての"泥だんご遊び"。中には、泥をさわったことのない子もいるんですよ。でも、手や足の裏でどろんこを感じ、夢中で作っていると、5歳でもピカピカの泥だんごを作れるようになります。そうやって作っていくうちに、『◯◯ちゃんが壊した』とか『◯◯ちゃんのが上手だった』って先生に教えてくれたり、子どもたち同士で『サラサラの砂は、どこどこのがいいよ』って教え合ったりするようになりますね」
"触れる"という体験をベースに表現力が磨かれたり、人との関わりが生まれたりしていく。つまり、五感を使う体験は、幼稚園教育要領に示される、保育の内容である5つの領域「健康(心身の健康)」「人間関係(人との関わり)」「環境(身近な環境との関わり)」「言葉(言葉の獲得)」「表現(感性と表現)」を育むことに繋がっているのです。
学生の感性を磨く
柿本さんは、保育を学ぶ学生にも五感を使う大切さを知ってもらいたいと、比治山大学でのレクリエーションの時間を使って、五感力を磨くための授業を行っています。街を歩いて、どんな匂いがするか? どんな音が聞こえてくるのか? などを調査して「五感地図」を作ったり、昔どんな遊びをしたのか学生同士で思い出を語り合ったり、朝起きてから寝るまでどんな五感を使っているかチェックしたり、二人組になって笑う、怒る、泣く、驚くなど、さまざまな表情を確認し合ったり...。
日頃、気にとめていなかった五感を意識すると、私たちがどれだけ五感を使って生きているのか、改めて気づかされます。そして、子どもたちが五感を磨いていける環境を作る大切さにも、気づかされるのです。けれど、実際に学生が保育者になったとき、子どもたちにただ五感を使わせるだけでいいのでしょうか。
柿本さんが、幼稚園の子どもたちの五感を磨くプログラムを作るときは「私たちが故郷で遊んだ体験を思い浮かべるのと同じように、子どもたちが将来ここで遊んだ体験を思い浮かべることができるだろうか」と考えるそうです。
「感動した、もっとやってみたい、上手になりたい、創りたい。そんな心に灯がともるような体験をしたら、将来それを自分の子どもにも繋いでいこうっていう気持ちが起きるんじゃないかと思うんです。それが、五感を使う本当の意味なんじゃないのかなって」
心に灯がともる――それは、自分が成長できるきっかけとなった楽しい思い出として、大人になってからもずっと消えずに燃え続ける灯なのでしょう。柿本さんが言うように、そんな体験をしたら、その楽しさを子どもたちにも体験させてあげたいと思うかもしれません。実際私たちも、両親、親戚のおじさんおばさん、先生など、たくさんの大人たちから、そんな遊びを教わってきたのではないでしょうか。そして遊んでもらった子どもたちは、また次の世代へと遊びを繋げていく。そうやって子どもたちは五感を使う遊び方を学び、たくさんの力を身につけてきたのでしょう。でも、今は社会環境の変化から、昔と同じような遊びを伝えにくくなってしまいました。
遊びを活用できるようにする
柿本さんは「今の学生たちは、昔のような〝心に灯がともる〟体験が少ない」と言います。それは、学生たちの授業での様子から感じられるそうです。
「毎年、授業でカリンバ(アフリカの民族楽器)を作っており、板を鋸で切ってドリルで穴をあけ、鋼をつけていくのですが、学生は板を切るときに使う鋸が使えないのです。それに、竹を割るときの鉈も使えない。ドリルで真っすぐに穴をあけることも難しい。これは、生活の中で体験する場がなくなってきたということですね。モノとの出会いも少ない、つまり、知恵がついていない、試行錯誤していないんです。遊びは学び。上手に作るために『ああやって、こうやって』って悩んで、『◯◯ちゃんが作っているようにするにはどうするんだろう?』って考えて。そうやって試行錯誤しなければ、心に灯はともらない。心に灯がともった経験がない学生が、保育者になったら、子どもが試行錯誤しないもの、心に灯がともらないものを渡してしまうかもしれないですよね」
そこで柿本さんは、レクリエーションの時間を活用して、学生たちが試行錯誤するような遊びも取り入れているのだそうです。
「まずは学生たちに竹でコップやお箸を作ってもらって、そのあと竹で自由に作品を作ってみてって言うんです。そうすると、思ってもみないものが生まれる。独創性が生まれてくるんです。ただ、コップやお箸を作らされただけじゃ、感動しないし、心に灯はともらない。それを活用して使わないと、遊びじゃないんです。ほかにも、広告や新聞紙でどんなものが作れるか設計図から考えてもらったりするんですが、『鳥かごできた』『ピアノができた』『スカイツリー作った』とかって、いろいろなものが出来てくるんですよ。それらは本当に独創的なんです」
学生たちに"心に灯がともる"原体験をしてもらい、その大切さを感じ、子どもたちにも伝えてほしい。柿本さんの授業からは、その思いが強く伝わってきます。
「私は保育って、学生に子どもをどういう風に指導するか、ただハウツーを教えればいいんじゃないと思うんです。保育者になる試験だけ受ければいいんじゃない。自分が体験してきた遊びを活用できる、遊びを楽しめる学生になってほしいんです。遊ぶことを知らない学生は、ただ子どもを遊ばせるだけの遊ばせ屋になってしまう。子どもたちの心に灯がともるような遊ばせ方をしてあげられる保育者になってほしいですね」
最近では、一時保育を行う場所などもどんどん増え、多様化し始めている保育の世界。柿本さんは言います。
「保育は『人、物、出来事』の出会いを生かし、子ども一人ひとりが思いや個性を発揮しながら共に育み合う営み。そして、周囲の様々な場や物に興味や感心を持って関わり、『楽しい』『もっとやりたい』と心弾ませて夢中になって遊ぶ中で、『心に灯をともす』豊かな体験をつんでいくところです。そんな子どもたちの笑顔を生み出す、幼稚園・保育園でありたいですよね」
そのために幼稚園や保育園はもちろん、大学でも、レクリエーションはますます必要なものとなっていきそうです。
プロフィール
柿本因子(かきもと よりこ)
比治山大学短期大学付属幼稚園園長、比治山大学短期大学部幼児教育科教授を務め、長年保育の現場に携わり続けてきた経験を、大学での人材育成に活かしている。大学での主な担当科目は、保育内容(表現)、音楽表現、レクリエーション概論・実技。(公財)日本レクリエーション協会理事。