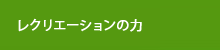地域に元気倶楽部をつくろう!
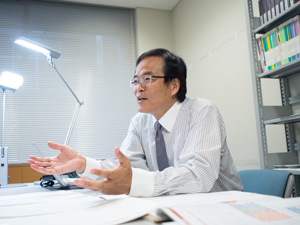 松尾 哲矢 氏
松尾 哲矢 氏
(立教大学コミュニティ福祉学部長)
中高年層の人たちが健康づくりに取り組み、交流を楽しむ仲間の輪。 これまでスポーツに距離を置いてきた人たちも参加しやすく、 そこでの交流が地域のきずなをつくることも期待されています。
今月の特集は、そうした地域の"元気倶楽部"を紹介。 インタビューでは、立教大学の松尾哲矢教授に、 中高年層へのアプローチ方法を伺いました。
これからの課題は、健康寿命をどうやってのばすか
今回お話をお聞きしたのは、立教大学でコミュニティ福祉学部長を務める松尾哲矢教授。松尾さんは、日本レクリエーション協会が文部科学省の委託を受けて行った「高齢者の体力つくり支援事業」や「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進のための調査研究」に関わってこられました。
松尾さんは、中高年層がスポーツに親しみ、仲間との交流を楽しむ機会や場が、「今の日本の現状から見ても重要だ」と言います。
「健康寿命という言葉をご存知ですか? これは、世界保健機関(WHO)が2000年に提唱した指標で、平均寿命から寝たきりなどの介護状態の期間を差し引いて算出します。2010年の日本の男性の平均寿命は79・6歳で、健康寿命は70.4歳。女性の平均寿命は86.3歳で、健康寿命は73.6歳。男女ともに、約10年も介護状態を余儀なくされているんです(*1)」
できることなら寿命を迎えるその日まで、自分の足で歩きたいというのが、多くの人の理想。しかし現実は、理想と大きくかけ離れているようです。もしかすると、健康寿命をのばすためのアプローチを考え直す時期にきているのかもしれません。
「運動には『必要としての運動』と『欲求としての運動』という、2種類があります。前者は、体のために仕方なくやる運動で、後者は、楽しむためにやる運動。つまり、後者は遊びながら健康で元気になれるんです。これまでの日本は、運動やスポーツで"楽しさ"ってちょっとしたタブーだった。『もっと頑張れ!』って言われて、楽しむためにやっている人たちは、ちょっと下に見られてしまう。でも、そんなタブーはもう終わりなんじゃないでしょうか。"楽しさ"の力に注目が集まり、一人ひとりがもっといきいき生きていく時代がきたと思うんです」
松尾さんは、楽しむための運動を提供できるのは"レクリエーション"であり、これからの日本を担っていくものだと言います。そして、そのような運動を必要とする中高年層がどれだけいるか、資料を参考に話してくれました。
「これは、各世代がどのくらい運動やスポーツを行っているのかがわかるデータです。高齢者の欄を見ると、例えば70歳以上で週に3日以上運動している方は53・6%と多く、一見『結構やってるねー!』と驚くんですが、実は、運動やスポーツをやった人だけに聞いているデータなんです。データをきちんと見ると、全くやっていない人は、約4人に1人もいる(*2)。運動が必要な高齢者は、まだまだいるということなんですね」
対象の世代に合わせた アプローチを考える
こうした水面下にいる中高年層を集めるためには、どうしたらいいのでしょう。
「"ライフコース(life course)"という言葉をご存知ですか。その人がどういう背景で生きてきたかを表す、いわば人生の軌跡ですね。例えば、1938年生まれの75歳(2013年時点)は、戦争のただ中に乳児期、そして7歳で終戦を迎え青少年期に戦後の復興に向けた一番苦しい時代を過ごしている。一方、1948年生まれの65歳は、『もはや戦後ではない』といわれた1956年に8歳、『レジャー・ブーム』が流行語となった1961年に13歳を迎えていて、高度経済成長と共にあり、遊びの感覚も育んできた。つまり、今の60代が75歳になったときの高齢者像は、今の75歳とは違うんです。私たちは、多くの世代を"中高年層"とか"高齢者"と一括りで言っていますが、世代によって特徴は全然違う。これからのスポーツ支援には、対象のライフコースをきちんと踏まえることが重要になってくると思いますよ」
ライフコースをもとに分析すると、今の60代は物事を"機能"で選んでいた前の世代と異なり、"新しい""おしゃれ"などのイメージがあるものを選ぶ傾向にある、と松尾さん。それでは、60代には、どのようなアプローチをしたらよいのでしょうか。
「例えば、最近流行っている"山ガール"という言葉。これは、これまで通り言うと"登山する女性"です。でも、言い方を工夫するだけで、おしゃれに聞こえますよね。それから、服やグッズなどのスタイルを提供するという手段もあります。山登りには、こういう服を着る楽しみがありますよとか、テニスには、こういうラケットがあるんですとか、モノ自体をカッコいい、かわいいと思わせる仕立てにするんです。そうやって、戦略的なイメージづくりを行っていくといいのではないでしょうか」
私たちが具体的に工夫するとすれば、中高年層、特に高齢者のイメージを払拭できるおしゃれな名前をつける、メンバーの募集チラシに新しさを感じさせる要素を加える、ユニフォームをかっこいいものに揃えるといった具合でしょうか。もう一度、そうした視点から仲間づくりの方法を考えても良さそうです。
さらに"新しい"イメージを好む60代にも、グラウンドゴルフ、ユニカールなどのニュースポーツはおすすめと、松尾さんは言います。
「ニュースポーツは、さまざまなスポーツの中でも、人気があるものに分類されます。しかも、年齢が上がるほど人気が上がっている(*2)。これは年齢を重ねることによって、競技スポーツで勝負をするよりも、みんなと交流を楽しみたいと思う人が増えていくからでしょう。高齢になるほど、人と人とのふれ合いは減っていく傾向にある。スポーツは、そんなふれ合いを楽しめる貴重な機会ですからね」
その世代の背景をきちんと把握し、交流にも重きを置く――確かに、これからのクラブづくりには、こうしたアプローチが必要なのかもしれません。
多様な楽しみ方を、バランス良く取り入れた環境づくり
松尾さんは続いて、集まった仲間が楽しめる環境づくりの大切さについてもふれます。
「集まってきた人たちに気持ちよくやっていってもらうためには、一人ひとりに合ったメニューを、どう提供できるかが大事です。ニュースポーツの人気が高まっていることから見ても、中高年層が楽しむスポーツは多様化してきています。活動の中に、競技・ふれ合い・自己表現・交流など、さまざまなタイプの楽しみ方をバランス良く入れ、いろいろな人が主役になれる工夫をしたいですね」
中高年層の人たちは、これまでにいろいろな経験もしてきています。その経験や得意分野を生かして、仲間に教えたり、アドバイスをする。そうやってクラブ内で支え合い、成長していけば、新たな自分の発見にも繋がるでしょう。
さらに、松尾さんは〝競争〟の捉え方についても、きちんと考える必要があると話します。
「競争は、勝ち負けではなく、仲良くなるための手段であり楽しむための手段。〝技〟を評価の対象とし、お互いの技のすごさを認め合い尊敬し合えば、お互い笑顔で競い合えるはずなんです。そのためには、『うまくなったなぁ』と実感できるような指導も時には必要となるでしょう」
これまで「総合型地域スポーツクラブ」でも、交流づくりは目標とされてきました。しかし、サッカーなど一つの種目を追求するメンバー・会員が多かったため、クリスマス会などの定期イベントはあっても、日常的な交流や他種目との交流にまで至ることは、ほとんどありませんでした。今、そのような状況を変えるために、いろいろな種目をみんなで楽しみ、交流できる仲間の輪をつくるときがきたのかもしれません。松尾さんは言います。
「大学って、行っても行かなくてもいいような、楽しむためのサークルがあるんです。しばらく行ってなくても、行けばいつでも歓迎してくれる。クラブっていうと運動部的なものが多くて、大学のサークルのような楽しみを共有できるクラブって、なかなかないんですよね。もし地域の中にできれば、50代60代になったときでも、横の繋がりが続いているかもしれません。サークル的クラブによって、これからの中高年の道筋ができていく。そんな未来もあるかもしれませんね」
プロフィール
松尾哲矢(まつお てつや)
立教大学コミュニティ福祉学部長。大学院コミュニティ福祉学研究科委員長。教授。博士(教育学)。専門はスポーツ社会学。著書に『福祉社会のアミューズメントとスポーツ』、『身体感覚をひらく―野口体操に学ぶ』など多数。