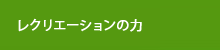いろんな人がいるから楽しい 遊びの力で「群れ」を育てる
 田上 不二夫 氏
田上 不二夫 氏
(教育学博士、東京福祉大学大学院心理学部教授)
特別支援学級の児童が元学級に戻るには......、不登校児が通学するようになるために......、これまでのカウンセリングでは、問題を抱える子どもを直すことに重点が置かれていました。
田上教授の開発した対人関係ゲームは、問題を抱える子ども=個を変えるのではなく、その子が属する集団を遊びにおける「群れ」とみなし、その集団を変化させていきます。遊びの力で集団を育てる「対人関係ゲーム」について、お話をうかがいました。
対人関係ゲームとは 遊びを通して集団が変わる
「人は初めての相手と会う時に、緊張や不安を感じますよね。対人関係ゲームでは、その緊張・不安を『遊び』によって解消し、より良い人間関係をつくっていくのです」
活動的な遊びで、身体運動反応や声を出すことにより、緊張・不安は抑えられます。また、遊びの楽しさやドキドキ感によっても、それらは抑えられ、集団の中に入っていけるようになります(拮抗動作法*)。対人関係ゲームは、その原理を利用した集団づくりためのカウンセリング技法なのです。
田上教授は、不登校やいじめ、学級崩壊など学校で起きている問題は、対人関係ゲームによって学校という集団・環境をつくりなおすことで解決できると提案しています。
個から集団へ これまでのカウンセリングとの違い
今までは、人間関係に問題がある場合、不登校児や障がいを持つ本人(個)が努力して変容し、学校なり社会(集団)へ適応することが求められてきました。田上教授が教育相談にかかわった当初も、行動療法やプレイセラピーにより、個を変えようとしていたのです。
ところが、学校に通うことが困難な子どもが大学の相談室に来ます。カウンセリングを重ねるうちに、生き生きしてリラックスしてくる子どもが、学校の門の前で硬まってしまう。学校という集団の中に入っていけないのです。または、特別支援学級には登校できるが、元の学級の教室には、入れないというケースもありました。
そこで、個を変えるのではなく、受け入れる集団側が変わらなければならないという思いを強くするようになりました。
「この人変わってるけど、でも一緒にいると楽しいよね、みんながそう言って受け入れるようになれば、障がいをもっている子どもも学校生活が送りやすくなります。障がいのある子どもに変容を求めるより、柔軟性のある人の方が変われば良い、いろいろな人がいるのが『当たり前』の学級ができれば、問題は起こらなくなります」
そこで、受け入れられる集団をつくるために開発されたのが、「遊び」を使った対人関係ゲームだったのです。
対人関係ゲームによる 交流から折り合いまで
対人関係ゲームは交流、協力、連携、心を通わす、他者と折り合うという5段階にわけられます。ゲームは、学級担任などがリーダーとなり、運動量が多く不安や緊張を感じにくいものから、次第に言葉を交わしたり、スキンシップを必要とするものへと段階的に進めていきます。
最初の交流の段階では、ジャンケンを使った簡単なゲームが使われます。次の協力するゲームには、「凍り鬼」というものがあります。鬼にタッチされるとその場で凍り、他の人がタッチして助けてくれるのを待つというものです。身体を十分使いながら、助け合う喜びを体験できます。ここまでで一緒に遊んでいる仲間たちに集団意識ができてきます。
ここで登場するのが、連携・役割分担するゲーム「くまがり」です。これはくま、きつね、きじの三すくみの関係を含む鬼ごっこです。くまはきつね、きつねはきじ、きじはくまをそれぞれ捕まえることができます。ルールはかなり複雑で、チームのそれぞれが役割分担して協力しないと味方の勝利は得られません。しかし、作戦を立てたり、友達とスキンシップしたり、これまでになかった楽しい体験ができ、休み時間に自発的に子ども同士が声をかけあって「くまがり」で遊ぶ姿が見られるようになります。
集団が形成されれば、次には集団の中の個の尊重へと導きます。この段階では心を通わすゲームを行います。2人1組で相手の印象やイメージにあった木を探してプレゼントする「わたしの木」というゲームがあります。相手への理解を深めながら、人に心をかける、かけられる喜びを経験します。
最後に行うのは他者と折り合うゲームです。「新聞紙タワー」というゲームでは、5、6人のグループに別れて、新聞紙を使ってタワーをつくります。一番高いタワーを建てたチームが優勝というシンプルなゲームですが、チームプレイなので、他者の考えを尊重し、自分の気持ちも大切にしていくことを学びます。他人と折り合い自分と折り合って、力を合わせ目標を達成する経験をするのです。
各ゲームの後には「振り返り」をして、それぞれが感想を述べます。「特に『折り合い』のゲームの時には、振り返りが重要です。他のチームは高いタワーをつくれたのに、どうして自分達のものはうまくできなかったのか。それまで仲の良かった集団が、険悪な雰囲気になることもあります。でも、どうすれば折り合いをつけて、より良い結果を得られたのか、皆で話し合いをすることが大切です」
A子さんの場合 不登校から元学級復帰まで
対人関係ゲームは、それに参加することによって、いろいろな人間関係を経験するゲームです。対人関係ゲームでは集団を「群れ」と呼びますが、ゲームを通じて「群れ」が良い人間関係を築くことができるようになります。
一例を挙げます。A子さんは不登校の時期を過ぎ、特別支援教室に登校できるようになりました。そして、好きな授業がある時は、元の教室に向かうまでになったのですが、自分から話しかけることはなく、他の児童も話しかけていいものかどうか迷っているようすでした。
ここで、担任がリーダーとなる対人関係ゲームを導入しました。A子さんの「凍り鬼」の「振り返り」には「最初はあまりやりたくなかったが、やってみると楽しかった。たくさんの人に助けられて嬉しかったが、助けることができずがっかりした」という言葉が見られました。
対人関係ゲームを進めていくにつれ、A子さんの緊張がほぐれ、それを見ている同級生の態度も変わっていきました。腫れものにさわるようだったのが、気軽に声をかけるようになります。集団が個を受け入れたのです。
頃合いをみて、担任が明日から元の教室に来ないかと尋ねると、行きますと返事がありました。その後は、不登校前は孤立していた休み時間も、皆と遊ぶようになりました。
A子さんがクラスに戻るとともに、学級にも変化が見られました。ゲーム導入前には小グループ化していた女子が、全員まとまってきました。また、以前は友達の輪に入れなかった児童が入れるようになったり、人間関係づくりが促進されました。個と一緒に集団も成長したのです。
「遊び」の力で集団を育てる 人とつながり 人と人とをつなぎ人をいかす
従来のカウンセリングは、対象に「課題」を与え、問題解決とともに一人ひとりの能力を伸ばそうというものでした。そしてリレーション・自己理解を深めることを目的としています。
一方、対人関係ゲームでは、課題を与えず、「遊ぼうね」という声かけで「群れ」づくりめざし、問題を抱える個を受け入れられる集団へと育てていきます。「遊び」の中に埋め込まれた学習を通して、子どもたちは自然にいろいろなことを発見し、学んでいく。そこには、振り返りの時には出てこない「言葉にならないものがたくさんある」と言います。
田上教授は、対人関係ゲームを組織的に発展させて、将来的には特別支援学級がなくなることが理想だと考えます。
「仲間の中で子どもは伸びていくのです。障がいのあるなしではなく、それぞれの子どものニーズに応える教育をしていかなければなりません。今までは病んでいる人・個を育てていましたが、これからは集団を育てることが求められます」
ゲーム・遊びによって人間関係を良くしようというのは、レクリエーションにも通じます。
「『遊び』には楽しいだけではなく、その『群れ』の一人ひとりを成長させる力があるのです。レクリエーションも同じだと思いますが、最初は簡単なゲームなどで、交流をめざしますよね。リーダーは、交流ゲームに留まるのではなく、『遊びの力』を使って、意図的にその集団を成長させていっていただければと思います」
遊びの効用
・緊張・不安を吹き飛ばす
・参加しやすい
・社会的行動の促進
・ストレスから解放
・自発性、創造性を触発
・協力しあうことで人間関係の欲求が充実
・役に立ち必要とされて自信がつく
・一緒に楽しい体験をして仲間意識が育つ
・集団遊びは、ソーシャルスキルを獲得
・ルール遵守の習慣
プロフィール
田上不二夫(たがみ ふじお)
1945年、東京生まれ。カウンセリング心理学者。教育学博士(筑波大学)。東京教育大学助手、筑波大学講師、信州大学助教授、筑波大学教授を経て、東京福祉大学・大学院心理学部教授、筑波大学名誉教授。日本カウンセリング学会元理事長。認定カウンセラー、上級教育カウンセラー。
著書:『対人関係ゲームによる仲間づくり--学級担任にできるカウンセリング』(編著)、『特別支援教育コーディネーターのための対人関係ゲーム 活用マニュアル』(共編著)ほか