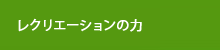障がいのある人もない人もみんなで楽しむ スポーツ・レクリエーション
 野村 一路 氏
野村 一路 氏
(日本体育大学レジャー・レクリエーション学教授)
日本レクリエーション協会が文部科学省から委託を受け、 全国各地で展開している「健常者と障害者の スポーツ・レクリエーション活動連携推進事業」。本事業協力者会議の座長を務める日本体育大学教授の 野村一路さんに、今回の事業で、レクリエーションが どのように役立てるのかお聞きしました。
レクリエーションだから できること
「健常者と障がい者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業」は、「スポーツ基本法」の第2条基本理念に、障がい者のスポーツ推進に関する内容が盛り込まれたことを踏まえて立ち上げられた新規事業です。事業のねらいは、障がいのある人もない人もスポーツ・レクリエーション活動を一緒に楽しみ、地域で共に生きる仲間づくりをしていくこと。
野村さんは、この事業でのレクリエーションの役割について、こう話します。
「今、社会問題となっているのは〝体を動かしていない〟こと。特に、障がいのある方は、障がいの内容や程度にもよりますが運動不足になりがちです。でも『スポーツ』というと、〝苦しい〟とか〝頑張らなければならない〟というイメージから、嫌だなと思う人が出て来てしまう。それが、『レクリエーション』となると"楽しい"というイメージを持てるため、入り口として入りやすくなると思うんですよね」
事業の敷居を下げ、親しみやすくなる。レクリエーションの役割は、それだけにとどまりません。
「本来レクリエーション活動とは〝明るく豊かな生活を送るために、自ら望んで行うプログラム〟を指します。つまり、その方にとってそのプログラムが楽しければ、レクリエーション。ビールを飲むのも、石を集めるのも、本人が楽しみとしてやっていればレクリエーション活動です。そういう意味でいうと、実はスポーツ活動もレクリエーション活動の中に含まれます。バスケットボールを楽しみとしてやっていれば、その人にとってそれはレクリエーション。ただし、付き合いでしょうがなくやっているのであれば、違います。つまりレクリエーション活動は、一人ひとりの捉え方によって変わるもの。私は、さまざまな人や地域を対象に行われる今回の事業では、そのような考え方がとても大切だと思うんです」
レクリエーションは、その対象によって提供する内容が変わります。今回の事業で言えば、障がいのあるなしに関わらずその地域に住む方のニーズをくんで、その人たちが地域の生活において何を望んで何をしたいのか、その地域の資源をどう使いこなしていけばいいかなどを考えた上で、一人ひとりに合ったプログラムを考えていくことになるわけです。そして、それこそがレクリエーションだからできることなのだと、野村さんは話します。
セラピューティック・ レクリエーションを参考に
今回の事業で、障がいのあるなしに関わらずプログラムを提供するために取り入れられたのは、福祉レクリエーションの援助過程にある「APIE(エーパイ)プロセス」という考え方。これはイベントやプログラムを行う際、事前に対象者の情報収集をしてどうサポートするか計画し、実際にイベントやプログラムを行った後もきちんと評価し、次のイベントやプログラムへ繋げていくというものです。
野村さんは、APIEプロセスをより効果的に活用するためには、「セラピューティック・レクリエーション[Therapeutic Recreation](以下TR)という考え方が参考になる」と言います。
「例えば、それまでゴルフ三昧だった方が、事故で足を切断して車椅子を使う生活になってしまったとします。そうしたらTRは、その人が生きる楽しみを取り戻すために、車椅子でもゴルフができることを教えてあげるんです。車椅子でもゴルフのできるゴルフ場はどこにあるのか、どういうクラブを使うのかはもちろん、その方に合う仲間を紹介したり、ゴルフをするためのお金をどこから手当てするのかも、一緒に考えたりする。つまり、ただ単に車椅子ゴルフの存在を教えるだけではなく、必要な段階で必要な支援をし、最終的にその人だけでゴルフを楽しめるように導いていくんです」
TRはレクリエーションプログラムを、その人が自ら主体的に選択し参加できるようになるまで導く役割を担っています。今回の事業で障がいのある人とない人とが意図的に交流できるような場を作り、継続的に日常生活の中で楽しむためには、TRの手法を参考に、参加者に合わせたアプローチを行うことが大切です。重要なのは、その人にとって楽しいと感じられること。そのためには、何が楽しいのか? を把握しなければなりません。その際に、APIEプロセスの手法が活かされてくるのです。
レクリエーション支援を考えるときには、集団でプログラムを考えがち。同じプログラムを行う場合でも、TRの考え方を参考にAPIEプロセスを活用していけば、一人ひとりに対してアセスメントを行いアプローチしていく、個性を尊重したレクリエーション支援の必要性を再考するきっかけにもなります。
大切なのは、不安を取り除いてあげること、「楽しい!」「一緒に楽しめる!」と、みんなが思えることなのです。
みんなが人生を楽しもう、 と思えるように
野村さんはTRのような役割を、福祉分野のレクリエーションの専門家である福祉レクリエーション・ワーカーに担ってもらえたらと期待します。
「大切なのは、その地域の人たちが何を望んでいるのかをはっきりさせ、地域の資源をどう使いこなして、どう解決していくのか目標を定めること。そのための手段は、スポーツ活動だけじゃなくてもいいし、一人ひとり趣味嗜好が違うのだからみんな同じことをやらなくてもいいと思います。他の人と同じことをやらされて、対象者に『つまんない』って思われていたら、もったいないと思うんです。また、今回の事業のような場合には、人と人を繋ぎ合せる役割も担ってもらえたらいいですね。社会福祉やスポーツ関係の方などさまざまな分野の方が揃っても、うまくマネジメントする人がいないとせっかくの意見が繋がらない。それらの意見を福祉レクリエーション・ワーカーが繋ぎ、本当に適切なレクリエーションプログラムを検討し、自ら主体的にレクリエーション活動を行えるようになるためにはどんな段階を踏めばいいかを考え、支援していってほしいんです」
レクリエーションの重要性をまだ理解されない人や、どのように楽しめば良いのか分らない人が、自分で楽しめるところまで導いてあげられる存在――そんな役割を担う人がいれば、日本にも人生を楽しめる人がもっともっと増えていくでしょう。
最後に野村さんは、今回の事業で障がいのあるなしに関わらず、一緒にレクリエーション活動を行う意義について、こう話します。
「障がいに対する研究も進み、障がいがあると認識される方も増え、さらには超高齢社会を迎えていますから加齢に伴う機能低下も増す。これからの日本社会は、障がいのある方がもっと増えていくでしょう。これに適応していかなければ、社会生活が成り立たなくなっていく。それに誰だって、いつどこで障がいのある状況になってもおかしくない。でも、私たちは障がいのある方の実態を知りませんよね。だから、理解を深める必要があると思うんです。理解を深めるというのは、個人個人の違いを認めることに繋がります。今の世の中は、みんな価値観が違うということを認め合えていないと思うんです。私も違っていいんだ、それぞれが違う方が面白いんだ、って認め合わないと。今回の事業は、そのための突破口でもあると思います」
支援者の力によって、一人ひとりが自分のレクリエーションを見つけて輝き出せば、障がいがあってもなくても、誰もが豊かな世界を持っているのだと気づくことでしょう。さらに、そんな豊かな世界を目にすれば、「自分も人生を楽しまなきゃ」と思う人も出てくるに違いありません。野村さんは「レクリエーション活動は、そんな風にみんなの価値観を変えていくこともできるはずだ」と話します。
日本の未来を明るいものに変えていくために、レクリエーション活動はこれからもっともっと必要とされてくるのかもしれません。
プロフィール
野村一路(のむら いちろ)
日本体育大学レジャー・レクリエーション学教授。主な研究内容は、生涯スポーツ、障害者スポーツ、レジャー・レクリエーション。1998年の長野冬季パラリンピックで、ベニューアドバイザー(会場運営するアドバイザー)を務める。そのほか、障がい者のための研修会や講習会の講師も数多く務める。