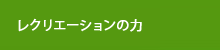福祉レクリエーションで現場がかわる!
 秦野 吉徳 氏
秦野 吉徳 氏
(通所リハビリ はまおか所長)
マーレー寛子 氏
(デイサービスセンターむべの里 施設長)
福祉サービスの利用者が、本人らしい楽しさを 追求することを様々なレクリエーション活動を用いて支える「福祉レクリエーション」。その実際を、施設経営者としてご活躍の、秦野吉徳さんとマーレー寛子さんに伺ったところ、利用者にも職員にも笑顔をもたらしている様子や、施設経営の視点からの重要性が浮かび上がってきました。
ぼくらはプレゼントを もらえるいい仕事
――理学療法士であり、デイケアセンター"はまおか"の所長をされている秦野さん。デイサービスセンター"むべの里"の施設長をされているマーレーさん。お二人とも「福祉レクリエーション」を重視した施設運営をされていますが...。
マーレー 私は、利用者の楽しさや生きがいにつながっていく福祉レクリエーションが、大切だと思っています。
秦野 そうですね、実は、病院理学療法士として怪我や病気になられた高齢者のリハビリを担当していた頃は、身体機能が回復し生活動作が自立できれば元の生活に戻れると考えていました。デイケアを始めてみてわかった事は、要介護高齢者の生活の質は、身体や生活機能の回復だけでは不十分で、心のケアなくして"自律"はないということに気づかされたのです。普通の生活をしていくために本当に大切なのは、生きる心の力なのだと感じました。障がいを持つとその心の力が弱くなってしまいます。楽しみや喜びを共有できる福祉レクリエーションは、生きる心の力に再び灯をともしてくれるんです。
マーレー 利用者の心に再び灯をともす楽しさは、確かにありますね。うちの施設では、福祉レクリエーションの一環として、習字、ものづくりなどの「講座」を実施しています。意欲が低下し、自分ができる講座はないって決めつけるようなマイナス思考の利用者がいらしたんですが、それらの講座の一つである健康体操に参加して、長く続けるうちに少しずつ上手に動けるようになったんですね。今は、自分の楽しみはこれ! って感じになっています(笑)。マイナスからプラスに気持ちが大きく変わっていったんです。
――うれしいお話ですね。他にも講座で元気になられた方はいるんですか。
マーレー 何人もいらっしゃいますね。例えば、習字教室では、毎回講座に出て熱心に取り組んでいる方の作品が、施設内の展示で一番上に張り出されます。これってとても張り合いになるんですよね。銀行のフロアーや先生の関係の展覧会をお借りして行っている作品展では、作品を見た家族や近所の方から「おかあちゃん、がんばったなー」なんて、声もかかる。そういうことが励みになっているんです。こうしたことを励みに、だんだんと習字に夢中になって、今では「これが私の生きがいだ」と話してくれる方も何人もいらっしゃいます。
秦野 うちの施設の利用者に、3年前は自分の殻に閉じこもっていた方がいるんです。周りは、全部〝敵〟みたいに思っちゃっていて、他の施設では続かなくて、うちに来たんです。その方の担当が、福祉レクリエーションを学んだ職員だったんです。いろいろなレクリエーション活動を一緒に楽しみながら彼女の心を解かしてくれて、3年目には、心の灯が輝いているような絵手紙を描き上げたんですよ。これを持ってきた担当の職員は、うれしくて泣いていましたね。
マーレー 職員が光り輝く瞬間ですね。
秦野 そう。関わった方の笑顔が、職員の達成感。ぼくらの仕事って利用者から、そういうプレゼントをもらえるものなんですよね。福祉レクリエーションを学んだ職員(福祉レクリエーション・ワーカー)たちとも「大変なことも多いけど、1年に1回そういうプレゼントをもらえると、1年元気でがんばれるよね」って話をしています。
場面づくりを どう持っていくか
――利用者の心に、再び灯がともって元気になっていくために、どのような支援を心がけられていますか。
マーレー 一人ひとりに合った小さな目標を設定することが大切ですね。その人の能力からみて高い目標だと不安になってしまうし、低い目標だと退屈してしまいます。ポイントは、本人が「ちょっとがんばればできるかしら」と思える難易度の目標を決めることです。
秦野 そうやって階段を一段一段上がるようにしていくと、利用者の気持ちや行動が変容していくんですよね。例えば、「生きていてもしょうがない」と言って周りと壁をつくっていた女性の利用者がいるのですが、彼女は、福祉レクリエーション・ワーカーの職員との会話を通じて「人との会話っていいなぁ」って思うようになりました。それで階段を一段上がったと判断した福祉レクワーカーは、2人の会話にもう一人利用者を加えた3人の会話の機会を用意しました。この機会に彼女は会話を楽しみ、さらに一段階段を上がりました。そこで今度は、お茶を飲みながらおしゃべりができる喫茶コーナーで、他の利用者の会話に混じる場面をつくりました。そのとき、彼女が「仲間もいいな」って思ってくれた。つまり、もう一段階段を上がってくれたんですね。
マーレー どのように場面をつくるか、なんですよね。職員が良い場面をつくって、機会を提供することで、利用者さんたちが最終的に喜んでくれたり、仲間が引っ張っていってくれたりすることがあります。
秦野 そうなんですよ。彼女の場合、アセスメントで歌が好きなことがわかっていたんです。そこで「いいお声ですね」って声をかけた。そうしたら、「昔カラオケに行ってたんよ」って教えてくれて、会話から次のステップとしてカラオケへと進みました。さらに、歌う楽しみだけでなく、積極的に振る舞える自信を取り戻すことを目指した、もう一段上のステージに挑戦しました。それが、施設で開いていたカラオケ大会。そこで、彼女に優勝してもらったんです(笑)。賞状を渡して家に持って帰ったら、家族から「良かったね」って言われて。彼女は自信を取り戻して、今では周りとの壁がなくなったんですよ。
――すごいですね。階段を登った先に、そのような結果があるって予想していたんですか?
秦野 そういうことを頭に描きながら、こういう笑顔を見たいって思いながら、やっていますね。
マーレー 私達も、答えがあるわけじゃないけど、ある程度の筋書きは描いていますね。うちの施設では、トーンチャイム(ハンドベルのように、数人で音を分担して演奏する楽器)をやっています。少しずつ難しい曲に挑戦してできるようになる度に皆さんが夢中になっていきました。さらにやりがいを得てもらうためには賞賛されて、達成感を得られる場面が必要だと私達は考え、施設の中で披露する機会をつくりました。さらに、強く生きがいを感じてもらえるようにと、よそのデイサービスを訪問して、腕前を披露することを始めました。今では、自主的にすっごい厳しい練習をされています。やはり、人前で演奏したり喜ばれることでかなりの達成感があるんですね。家で、サランラップの芯を使って練習する方もいるんですよ。
秦野 よその施設に出かけるのは、再び心に灯をともす、すばらしい場面づくりですね。自分から何かをやろう、やりたいと夢中になれる気持ちって、大事だよね。
マーレー そうやってがんばった成果を出したときに大切なのは、その人ができるようになったことを、誉めること。フィードバックが良いと、そのときの体験を大切にするんです。何かいいことがあったという気持ちになる。
秦野 もともと人って、誉められたい、ありがとうって言われたいなど、欲のかたまりだと思うんですよね(笑)。だから、その欲を上手く利用した場面を作って「自分はちゃんとできるんだ」という自己効力感が高まるような環境を用意することが大切だと思うんです。
――カラオケ大会で優勝したり、他の施設でトーンチャイムの披露をしたりしてほめられたら、かなり自己効力感が高まりそうですね(笑)。
楽しむ能力があれば、 病気があってもしあわせ
――その人に合った階段(目標)を、少しずつ登っていくための環境を作る。階段を上がったら、きちんとフィードバックする。成功したときの喜びを、より大きくできる場を設定する。そういった福祉レクリエーションの支援ができる人がいると、施設にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
秦野 利用率が高い施設になりますよね。病院でお医者さんに「この日に来なさい」って言われても、「この日はデイサービスがあるから」って断るような、利用者が来たくなる施設になれます。
マーレー 職員の定着率を上げることにもつながります。建物にお金をかけるのではなく、職員を育てることが大事です。利用者が人間関係を築けたり、仲間意識を持てたりするかどうかは、職員にかかっているわけですから。
秦野 そのためには、職員にレクリエーションを学ぶ機会をつくってあげないと。レクリエーション協会がやっているような講座を受講して、ノウハウだけじゃなく、背景の理論的な意味づけがわかってくると、自分がやっていることの良さがわかってくる。そうすれば、私たちは利用者に力をあげられる場にいるんだ、って職員に気づかせてあげられる。
マーレー よく、レクリエーション担当になったから大変だっていう職員がいるけれど、そうじゃなくて、本当は職員にとって一番自己実現しやすい場にいるんですよね。
秦野 今は、ともすると職員が介護マシーンになっちゃう。あたたかな思いを持って介護の世界に入って来た人もいるのに、日々のケアに追われて離職したり「こんなはずじゃない」って、いろいろな施設を点々としたりする人も多いよね。そういう人も、福祉レクリエーションを学ぶと、この仕事は利用者にこんなに力をあたえてあげられるものだって気づけるんですね。
マーレー 機械的な介護では、福祉の仕事は楽しくないよね。人のしあわせ感、楽しみ感って、歩けない人が歩けるようになるってことだけじゃないんです。歩けなくても、楽しく生きている人はいるし、楽しさの尺度って人それぞれ。つまり、楽しむ能力があれば、病気があっても幸せを感じることはできるんですよね。福祉レクリエーションが職員にとって力になるのは、利用者の楽しむ能力を引き出し、支えられるようになるからだと思います。
秦野 利用者にあった楽しみを共につくるんですね。そのためには、利用者の想いに気づける力、それを実現するための発想力、そして利用者の楽しむ能力を引き出すための関わり力が大切です。こうした力があるかないかで、結果は大きく違ってきますから、こうした力を養えている福祉レクリエーション・ワーカーが、もっと増えていくといいですよね。
プロフィール
秦野吉徳(はたの よしのり)
2001年に通所リハビリ はまおかを開設。現在、市立御前崎総合病院 診療技術部長。リハビリセンター長。通所リハビリ はまおか所長。静岡県理学療法士会学術局長、聖隷クリストファー大学臨床教授。
マーレー寛子(まーれー ひろこ)
京都市立堀川高等学校卒業後、渡米。University of Georgia教育学部、University of North Carolina-Chapel Hill大学院でセラピューティックレクリエーションを専攻、地域障害者のレクリエーションについて研究。現在、社会福祉法人 小羊会、デイサービスセンターむべの里 施設長。福祉社会学博士。