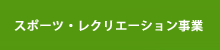スポレク事業が求めるスポーツの「楽しさ」
公益財団法人 日本レクリエーション協会
理事長 小西 亘
スポレク事業が求めるスポーツの「楽しさ」
 平成23年に「スポーツ基本法」が制定されて以来、公益財団法人日本レクリエーション協会は何をすべきか、考え続けてきました。この法律に新たに「スポーツ・レクリエーション」という言葉が取り入れられたことにより、「スポーツを通じて行うレクリエーション活動」が脚光を浴びることになったからです。あらためて、スポーツ・レクリエーション事業(スポレク事業)の在り方が問われているのです。
平成23年に「スポーツ基本法」が制定されて以来、公益財団法人日本レクリエーション協会は何をすべきか、考え続けてきました。この法律に新たに「スポーツ・レクリエーション」という言葉が取り入れられたことにより、「スポーツを通じて行うレクリエーション活動」が脚光を浴びることになったからです。あらためて、スポーツ・レクリエーション事業(スポレク事業)の在り方が問われているのです。
文部科学省からも「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進のための調査研究」、「高齢者の体力つくり支援事業」、「健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション連携推進事業」などの委嘱を受け、県・市町村レクリエーション協会の協力を得ながら、いろいろなスポレク事業について試行を続けてきました。
そして、その結果を分析し、今後、全国的に定着させるべきスポレク事業は何か、検討を続けてきました。その中で、スポレク活動を通して高齢期における活動的な生活習慣と地域での仲間づくりを促進する施策、例えば、その拠点となる「元気倶楽部(仮称)」を全国の小学校区単位に開設する新しいスポレク事業の構想が浮上してきました。この構想については、文部科学省のご指導を得ながら検討を続け、新しい文部科学省の委託事業として実現するよう準備を続けたいと考えています。
検討を続けるなかで出てきた課題がありました。スポレク事業はスポーツの事業なのかレクリエーションの事業なのかはっきりさせたい、ということです。当然のことながら「レクリエーションの事業」なのですが、それでは、スポーツとのかかわりはどのように考えたらよいのでしょうか。この事業の根幹にかかわることですので、私の考えを述べておきます。
心の健康を求める
 現在我が国で行われている「スポーツ」には二つの面があるように思います。一つは「勝敗を争う」という側面と、もう一つは「楽しさを求める」という側面です。前者では体力、技術を重視し、後者では協調性、やる気を重視します。この二つの面は不即不離の関係にあるのですが、我が国では母校の名誉とか地域の名誉という文化が強調され、勝敗が重視されてきたように思います。
現在我が国で行われている「スポーツ」には二つの面があるように思います。一つは「勝敗を争う」という側面と、もう一つは「楽しさを求める」という側面です。前者では体力、技術を重視し、後者では協調性、やる気を重視します。この二つの面は不即不離の関係にあるのですが、我が国では母校の名誉とか地域の名誉という文化が強調され、勝敗が重視されてきたように思います。
本来、「スポーツ」とは娯楽、楽しみ、慰み、という意味です。(休養・娯楽のための)運動、競技、という意味です。(体力・技術を競う)運動、競技ではありません。楽しいもののはずです。レクリエーションが重視しているものは、スポーツの「楽しい」という側面です。
人間は、「楽しい」という感情が高まった時、脳の中で「やる気」を引き起こす「ドーパミン」という物質が放出される。その「やる気」がさらに積極的に行動する意欲を生み出し、豊かな人生を創出する。これはある脳科学者の話です。
レクリエーション活動の目的は「人の心を元気にすること」、つまり「やる気」を起こさせることにあります。だから、その手段として行うスポーツは楽しいものでなければならない。勝敗にこだわるスポーツは、運動能力に恵まれない、勝利に貢献できない人々にとっては楽しいものではないのです。屈辱感が残るだけです。
レクリエーション協会の使命は、人々が「楽しい」と感じる「場」を準備することです。「楽しいと感じることのできる状態」とは、「心が健康である状態」です。「心の健康」と「体の健康」とは違います。
我々が現在進めている高齢者や障がい者に関わる事業も、求めているのは「心の健康」です。満ち足りた満足感です。高齢者や障がい者に、身体的な機能・能力の向上を求め続けることは限界があります。レクリエーション活動において求められるものは「心の健康」なのです。そこに、レクリエーションの特色があります。