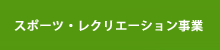異世代のスポレク交流をめざす
公益財団法人 日本レクリエーション協会
理事長 小西 亘
小学生(低学年)との交流を考える
新しいスポレク事業は、地域社会の空洞化や人間関係の希薄化という社会問題に対処するという命題のもとに始まりました。このような大きなミッションは、どこかに焦点を合わせて解きほぐしていかなければならない。私たちは、60代を中心としたニューエルダーといわれる世代を中心に地域の絆を強める、という構想で始めました。それに、高騰を続ける医療費を軽減するというねらいもありました。この構想について検討を続けるなかで、併せて検討すべき課題として出てきたのが「異世代の交流」でした。これは、地域社会の活性化を図るために、極めて重要な課題です。問題は、どこからはじめるかです。焦点を定めないと、問題は拡散し、成果が期待できなくなります。
私たちは、ニューエルダーと小学生(低学年)から始めたいと考えています。現在、三世代家族が少なくなった。核家族が中心です。住宅事業も関係があると思います。我が国では、三世代家族が地域文化の継承に大きな役割を果たしてきました。おじいちゃんと孫との関係、その疑似体験ができないか。ニューエルダーと小学生が共にスポーツを楽しみながら語りあうことに大きな意味があると思います。それに、体力的バランスが取れているのです。また、小学生(低学年)の参加は、両親の参加も期待できます。新しい世代との交流のきっかけをつかむことにもなります。
学校でのスポーツ嫌いは、小学校の低学年に始まるといわれています。仲間と共に体を動かすことの喜びは、人間の本源的なものです。学校体育の中でも、全ての児童が体を動かすことの楽しさを共有できるように配慮することが大切です。また、地域社会においても、近所の仲間とともに体を動かす機会が少なくなった、と聞きます。スポレク事業を行う中で、そのための「場」と「機会」を準備することは大きな意味があります。また、このたびの事業は、小学校区を単位とし、事業を行う施設の一つに小学校の体育館を予定しています。このスポレク事業の趣旨にもあっているように思います。
新しいカテゴリーのスポーツを開拓する
ニューエルダーと小学生との交流を核として行う場合、そこで取り上げる「スポーツ」は、すべてを既存のスポーツに依存することには限界があります。勝負にこだわらず、どこでもだれでも参加できる、という視点から考えると、新しいカテゴリーのスポーツを開拓する必要があります。参加者の負担軽減を原則とするスポレク事業においては、複数のスポーツ用具を準備することに経費面の制約があるからです。
みんなで楽しむというスポレク事業の趣旨からみれば、勝負にこだわるというスポーツは望ましくない、それに、数人で広い場所を独占するスポーツも望ましくない。スポレク事業には、スポーツへの参加者を増やす、という大きな目標があります。
日本レクリエーション協会では、現在、新しいカテゴリーのスポーツのアイデアを募集しています。全国のレクリエーション指導者の中には、多くの実践を積み重ねるなかで、素晴らしいアイデアをお持ちの方が多いと思うからです。新しいスポレク事業を広めるということは、全国のレクリエーション指導者の全面的なご協力を前提としています。これから始まるスポレク事業は、全ての市町村で、全ての小学校区で実施することをめざしています。スポレク指導者の活躍する舞台は全国的に広がります。
現在私たちが構想しているスポレク事業は、あくまで構想の段階です。国の委託事業が始まるかどうかはこれからの問題です。文部科学省をはじめ、関係行政機関の皆さんがこのスポレク事業をご理解していただけることを期待するのみです。
最も大切なことは、全国に広がるレクリエーション関係者の問題意識だと思います。我々に課されているミッションとは何か。待っているだけではダメなのです。みんなで考え、積極的に参加してください。そのことが、レクリエーションの社会的評価を高めることになるのですから。