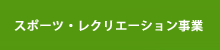新しいスポレク事業への道を探る
公益財団法人 日本レクリエーション協会
理事長 小西 亘
成人のスポーツ参加率を増やす
 文部科学省の委託を受けて実施した「ライフステージに応じたスポーツ活動推進のための調査研究」や「高齢者の体力つくり支援事業」の報告書を分析する中で、関係者に共通の焦燥感が出てきました。このままでは成人のスポーツ参加率は増加しない、ということです。「スポーツ基本法」に基づき文部科学省が作成した「スポーツ基本計画」の中に、成人のスポーツ参加率(週1回以上)をできる限り早期に65%(現状は45.3%)にする、という具体的な政策目標が揚げられているからです。
文部科学省の委託を受けて実施した「ライフステージに応じたスポーツ活動推進のための調査研究」や「高齢者の体力つくり支援事業」の報告書を分析する中で、関係者に共通の焦燥感が出てきました。このままでは成人のスポーツ参加率は増加しない、ということです。「スポーツ基本法」に基づき文部科学省が作成した「スポーツ基本計画」の中に、成人のスポーツ参加率(週1回以上)をできる限り早期に65%(現状は45.3%)にする、という具体的な政策目標が揚げられているからです。
実施した委託事業のアンケート(高齢者の体力つくり)によると、参加者の大部分がスポーツ経験者で、未経験者はほとんどいない(2%)という結果でした。参加者を募って実施したことにもよるのですが、新たな参加者を開拓することの難しさを実感しました。
成人のスポーツ参加率を高めるためには、従来スポーツに距離を置いてきた人たちに積極的に働きかけ、スポーツに誘う努力をしなければならない。単に希望者のみを集めるという従来の方式は全面的に改める必要がある、という共通の認識に至りました。
新しいスポレク事業は(元気倶楽部)、全ての国民を対象とする一種の国民運動として展開する必要があります。そのためには、市町村教育委員会が主催し、市町村レクリエーション協会が主管し、スポレク指導者が中心となって実施するという方式が前提となります。ここで最も重要なのは「指導者の質」です。このことについては改めて述べます。
スポーツ未経験者へ働きかける場合のキーポイントは地域の人間関係にあると思います。そこで、スポレク指導者の協力者として新たに浮かび上がってきたのが、地域社会に「パートナー」を置くという構想です。「パートナー」は地域社会の人間関係に詳しい人の中から委嘱したいと考えています。スポレク指導者に協力して、スポーツに距離を置く人たちをスポーツに誘うという役割を果たしていただく。スポレク指導者のみにこれを期待することには限界があるからです。「パートナー」にはスポレク事業についてある程度の知識。技術を理解していただくことになります。その具体的な内容は今後の検討課題です。
地域の絆を強める
 私たちが構想しているスポレク事業「元気倶楽部(仮称)」は小学校区を単位にしたいと考えています。もっと狭くしてもよいのです。参加者の顔がお互いに見える地域にした方が効果的だと考えているからです。「高齢者の体力つくり支援事業」の参加アンケートを読むと、支援事業で知り合った人との交流は少ないということです。その理由の1つは地域の広さにあると考えています。「交流」は必要なことなのです。
私たちが構想しているスポレク事業「元気倶楽部(仮称)」は小学校区を単位にしたいと考えています。もっと狭くしてもよいのです。参加者の顔がお互いに見える地域にした方が効果的だと考えているからです。「高齢者の体力つくり支援事業」の参加アンケートを読むと、支援事業で知り合った人との交流は少ないということです。その理由の1つは地域の広さにあると考えています。「交流」は必要なことなのです。
「元気倶楽部(仮称)」を構想した「ねらい」が2つあります。その1つが「地域社会の絆を強める」こと、2つ目が「医療費の軽減」です。「スポーツ基本計画」の中で、社会環境や価値観の急激な変化として最初に取り上げられたのが「地域社会の空洞化や人間関係の希薄化」でした。地域社会の人間関係を強めることは、現代社会の大きな課題です。「元気倶楽部(仮称)」のねらいはここにあります。地域を広げず、限定する必要があります。
もう1つのねらいは、結果的に医療費の軽減につながるのですが、地域の人たちが仲間と共に体を動かすことの楽しさを身につけて健康な生活を送る、ということです。そのため、この事業で取り上げるスポーツは「健康」という切り口で考える。スポレク指導者に求められる資質もこの点が強調される。「楽しさ」は当然のことです。そのでなければ長続きしないからです。「楽しさ」を求めて、地域の史跡を探訪するなど、文化的事業を加えることも考慮すべきだと思います。
「元気倶楽部(仮称)」は、全国に定着させるための新しいスポレク事業として構想したものですが、文部科学省の委託事業として実施してきた「高齢者の体力つくり支援事業」等を踏まえたもので、この内容を反省し、改善してきた結果であります。